■ エノン写像
\[
f_{a,b}:(x_1,x_2)\mapsto(1-ax_1^2+x_2,bx_1),\quad
(x_1,x_2)\in\mathbb{R}^2,\quad a,b\in\mathbb{R}
\]
天文学者のエノン (Michel Hénon) は1976年に発表された論文で, $(a,b)=(1.4,0.3)$のとき
この単純な2次元写像が複雑な挙動を示すことを 数値実験 (数値シミュレーション) により示した.
$b=0.3$ に固定して, ロジスティック写像の場合と同様に, 写像 $f_{a,b}$ を繰り返し作用させるとき,
点 $(x_1,x_2)$ がどのように変化していくのか その様子を見てみよう.
まず,初期点を $(x_1,x_2)=(0.5,-1)$ とする.
- "hm1.py"を使用
(クリックすると,Pythonのプログラムをダウンロード可能)
$a=0.2$ に対する軌道
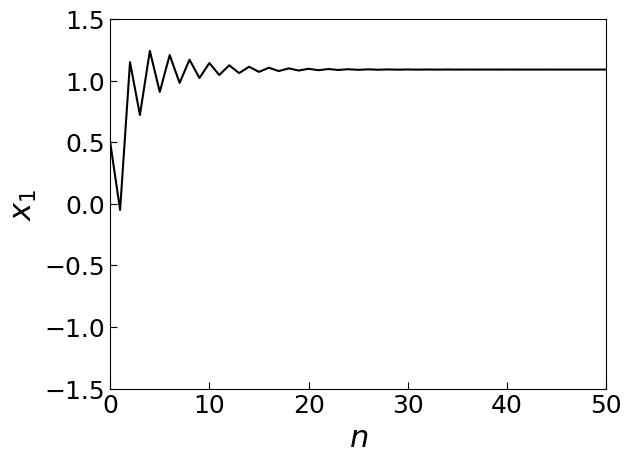
繰り返し数 $n\to\infty$ のとき軌道は不動点に収束する.
- "hm2.py"を使用
$a=0.5$ に対する軌道
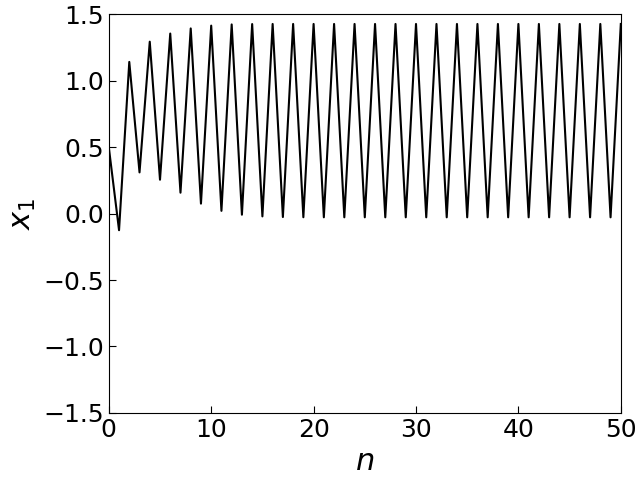
繰り返し数 $n\to\infty$ のとき軌道は周期2の安定周期軌道に収束する.
$a=0.3$ と $0.5$ の間で周期倍加分岐が起きている.
- "hm3.py"を使用
$a=1$ に対する軌道

繰り返し数 $n\to\infty$ のとき $x_n$ は周期4の安定周期軌道に収束する.
$a=0.5$ と $1$ の間で再び周期倍加分岐が起きている.
引き続き,$a$ の値を増加させていくと,ロジスティック写像の場合と同様に,
次々と周期倍加分岐が起こり,周期 $2^k$ ($k$ は4以上の自然数) の周期軌道が発生する.
(プログラムhm3.pyの"a = 1"の行を変更して実行し,確認してみよう.)
- "hm4.py"を使用
$a=1.4$ に対する軌道

いつまでたっても軌道にこれまでのような規則性はみらず,カオスが起きている.
変数 $x_2$ も含めて,$(x_1,x_2)$ 平面上で上の軌道を見てみよう.
- "hm5.py"を使用
$a=0.2$ に対する軌道

白丸は初期点と $n=50$ のときの点である. $n\to\infty$ のとき軌道は不動点に収束している.
- "hm6.py"を使用
$a=0.5$ に対する軌道
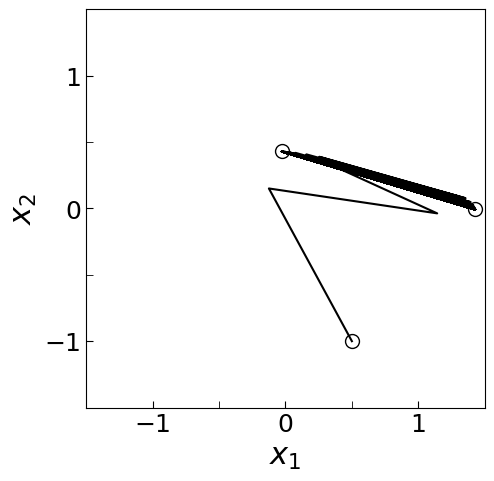
白丸は初期点と $n=49,50$ のときの点である. $n\to\infty$ のとき軌道は周期2の安定周期軌道に収束している.
$a=0.3$ と $0.5$ の間で周期倍加分岐が起きている.
- "hm7.py"を使用
$a=1$ に対する軌道

白丸○は初期点と $n=47$ から $50$ までのの点である.
$n\to\infty$ のとき $x_n$ は周期4の安定周期軌道に収束している.
$a=0.5$ と $1$ の間で周期倍加分岐が起きている.
上で述べたように,引き続き,$a$ の値を増加させていくと,次々と周期倍加分岐が起こり,
周期 $2^k$ ($k$ は4以上の自然数) の周期軌道が発生する.
(プログラムhm7.pyの"a = 1"の行を変更して実行し,確認してみよう.)
- "hm8.py"を使用
$a=1.4$ に対する軌道 ()

$n>1000$ のときの点をプロットし,計算された点は折線でつないでいない. 軌道はとても複雑である.
$n\to\infty$ としたときの収束先の軌道を アトラクタといい,
この例のように,不動点,周期軌道,不変トーラス (準周期軌道) と異なるアトラクタを ストレンジ・アトラクタという.
- "hm9.py"を使用
$a=1.4$ に対する軌道

上の図で1本の曲線に見えていたものが,何本かの曲線からなっていたことがわかる.
- "hm10.py"を使用
$a=1.4$ に対する軌道
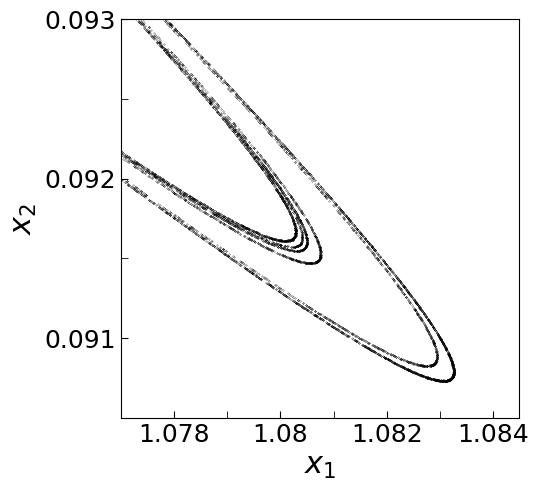
再び,上の図で1本の曲線に見えていたものが,何本かの曲線からなっていたことがわかる.
このように,拡大していくとき,同じようなものが繰り返し現れる幾何学的な構造を フラクタルという.
この例のように,ストレンジ・アトラクタは普通フラクタル構造を有している.
非常に依存したものとなっている. その変化の様子をもう少し詳しく調べてみよう.
- "hmb1.py"を使用
横軸を $b$,縦軸を $x_1$ として, 繰り返し数 $n$ が201から400までの点をプロット

ロジスティック写像の場合と同様に,安定な不動点からカオスに至るまで,
たくさんの(実は無限個の)周期倍加分岐が起きていることがわかる.
- "hmb2.py"を使用
区間 $[1.29,1.31]$ の $a$ に対して, 繰り返し数 $n$ が$201$から$400$までの点をプロット

ロジスティック写像のときと同様に,カオスが起きているような $a$ の値の範囲でも,
周期軌道の存在する範囲があり,そのような状態から先の図で見たのと同じようなプロセスを経て
再びカオスに至っている.
力学系の数値シミュレーション・トップページに戻る